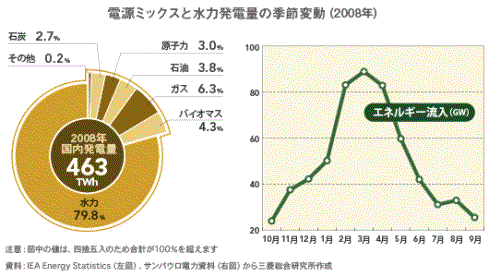△top 地理教育部会へ戻る
2011年 センター試験 本試験 地理 解説 2版
2011.1.15(土)実施
2011.1.19作成
T氏作成
地理B
第1問 (配点16点: 5 6 各2点、他3点) 【自然環境の地域性】
問1 1 ④ 【基本】大地形の断面図。新期・古期・安定陸塊の位置から判断。
A ザグロス山脈・イラン高原(新期)をへて中央アジアの平原(安定)。最後の●でキルギスのテンシャン山脈?(標高の高い古期)→③
B オーストラリアは東の大分水嶺山脈をのぞき安定陸塊→①
C ロッキー山脈(新期)をへて、カナダの平原(安定)。ロッキーはアンデスより東西の幅が広い。→④
D アンデス山脈(新期)をへてアマゾン低地→②
問2 2 ④ 【基本】チェルノーゼム・小麦 →イ
① テラローシャ・コーヒー栽培→エ
② レグール・綿花 →ウ
③ テラロッサ・果樹栽培 →ア
問3 3 ② 【基本】Cs →サンフランシスコ 都市の位置もあるので簡単
① Cw →釜山
③ Cfb →パリ
④ Df →モントリオール
|
都 市 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
| 150 |
San Francisco(6m) |
9.8 |
11.4 |
12.3 |
13.6 |
15.0 |
16.5 |
17.3 |
17.8 |
18.0 |
16.3 |
12.8 |
9.9 |
14.2℃ |
|
(37゚37'N,122゚23'W) |
106.6 |
91.2 |
88.8 |
28.5 |
8.0 |
2.5 |
0.9 |
1.4 |
5.5 |
26.6 |
62.0 |
79.1 |
500.9mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Paris(52m) |
4.0 |
4.5 |
7.0 |
9.5 |
13.5 |
16.3 |
19.0 |
18.6 |
15.2 |
11.4 |
7.0 |
4.9 |
10.9℃ |
|
(48゚58'N,02゚26'E) |
55.8 |
45.8 |
55.4 |
45.0 |
63.3 |
56.8 |
55.5 |
43.5 |
56.1 |
62.6 |
52.2 |
55.5 |
647.6mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 |
釜山(Busan)(69m) |
3.1 |
4.4 |
8.4 |
13.5 |
17.5 |
20.6 |
24.3 |
25.9 |
22.2 |
17.5 |
11.5 |
5.7 |
14.6℃ |
|
(35゚06'N,129゚02'E) |
37.8 |
44.9 |
85.7 |
136.3 |
154.1 |
222.5 |
258.8 |
238.8 |
167.0 |
62.0 |
60.5 |
25.0 |
1492.7mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 |
Montreal(31m) |
-10.2 |
-8.4 |
-2.3 |
5.7 |
13.4 |
18.2 |
20.9 |
19.6 |
14.6 |
8.1 |
1.5 |
-6.4 |
6.2℃ |
|
(45゚28'N,73゚45'W) |
72.2 |
61.2 |
77.9 |
76.4 |
77.0 |
85.9 |
87.2 |
99.3 |
97.5 |
75.4 |
92.6 |
87.6 |
990.3mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(『理科年表 平成20年版』) |
問4 4 ③ 【基本】河川流量は流域の降水や融雪から考える。北半球・南半球も注意。また、この問題は単なる流量ではなく、季節の割合である。注意が必要。
キ 雨季と乾季がはっきりしている。雨季が夏である。
→北半球でAwのK ガンジス川
ク 3つの中では一番季節変動が少ない→Af・AmのM アマゾン川
8 のコラムの図も参照
カ 345月に流量が多い→春先に融雪水が川に流れ込むL ミシシッピ川
<気候表挿入予定>
問5 5 ② 【基本】赤道の位置がわかれば、熱帯の位置はわかるだろう
② 安定陸塊で北はAw、南にAf→シ セイロン島(スリランカ)
① 安定陸塊で西にBS、東にAf→サ マダガスカル島
マダガスカル島は08年第1問問6に出題されたように南東貿易風によって島の東西で気候が大きく異なる。(Af・Aw・Cw・BW・BSあり)
③ 新期造山帯でAw→セ キューバ島
④ 新期造山帯でAf→ス フィリピン諸島
問6 6 ⑤ 【やや難】写真を含めた珊瑚礁の問題。
P グレートバリアリーフに集中。グレートバリアリーフの意味が大堡礁であること知っていれば簡単→チ 地図帳にも記載
R 沖縄などの南西諸島に集中。環礁でないことは想像したらわかるだろう。南西諸島は裾礁が多い→タ
Q マーシャル諸島のビキニ環礁やトラック諸島、モルディブ諸島→ツ
■珊瑚礁の分布図は目新しい。知識がなくても地図帳をよく見たり、日常の知識をうまく使って解くことも可能。問2土壌、問3ハイサーグラフ、問5大地形と気候は解きやすい問題であった。全体に標準的な問題である。
第2問 (配点18点:各3点) 【世界の資源と産業】
問1 7 ③ 【基本】原油の産出、貿易。注目する国に注意。
ウ サウジアラビアがない。また、日本があり、アメリカ合衆国が最大。アメリカ合衆国は生産量も多いが、世界貿易量の約25%を輸入する。→輸入
イ 西アジアやロシアもあるが、アメリカ合衆国や中国にもある→産出
ア イとは違い、アメリカ合衆国や中国にない。理由は消費量が多いため輸出余力がないため。→輸出
問2 8 ③ 【やや難】消去法で解く
① 原子力はスリーマイル島の事故(1979年)以来、新規原発建設を中断。2001年以降に政策を転換し新規の開発計画がでてきた。原子力の発電量は世界1位だが、米国内では石炭火力についで2位である。
② インドは国内の豊富な石炭(2007年世界生産3位)を使った石炭火力が中心。
③ 正解
④ ブラジルは豊富な水資源を利用した水力が8割に達している。世界最大のイタイプ発電所がある。ダムはブラジル高原にある。
■ブラジルの電源
鉱山エネルギー省(MME)が2007年11 月に発表した「国家エネルギー計画2030」(PNE 2030)では、2005~30年のエネルギー需要の伸びを年2.5~4.3%、電力需要の伸びを3.5~5.1%と見込んでいる。PNEの現実的な実行計画である「エネルギー拡張10カ年計画」(PDE)の最新版では、エネルギー需要増加率を3.6%、電力需要増加率を4.1%と想定している(PDE 2019)。
これに対するエネルギー供給は、再生可能エネルギーが45.9%(2008年、MME)と約半分を占めており、これはブラジルの大きな特徴である。ガソリンの代わりにサトウキビを原料とするバイオエタノールを利用していることや、電力供給を水力発電に多く依存していることがその要因である。実際にブラジルの電源構成を見ると、電力供給の約8割を水力発電が担っている(左図)。
しかし水力発電の最大の問題点は、降水量によって発電量が左右されることである。1年の間でも発電
量は月によって4倍もの開きがある(右図)。渇水に見舞われた場合には、電力供給の安定性に支障を来すおそれがある。実際、2001年には深刻な渇水から電力危機に見舞われた。このため水力発電のバックアップとして、ガス火力発電などの代替電源を確保することが重要な課題となっている。しかし、これまでブラジルは天然ガスの産出が少なく、主にボリビアからのパイプラインによって、天然ガスを確保せざるをえない状況にあった。
ブラジルのエネルギー事情に大きな変化をもたらしたのは、2008年末にサンパウロ州とリオデジャネイロ州沖で発見された深海底油田(プレサル油田)である。 それ以前のブラジルの石油確認埋蔵量は140億バレル程度であったが、プレサル油田の埋蔵量は110億~160億バレルと推計されており(ペトロブラス:ブラジル石油公社)、ブラジルの石油賦存量は一気に倍増することになる。プレサル油田ではガスも併産されるが、さらに2010年にはブラジル北東部にも大規模な内陸ガス田が発見された。ブラジルは近年、すでに石油の純輸出国になったとみられている(米エネルギー情報局推定)が、ルーラ前大統領は天然ガスについても自給自足の方針を打ち出しており、今後は天然ガスの輸出国になる可能性もある。
再生可能エネルギーを活用するエネルギー供給構造の上に、さらに石油、天然ガスというカードをも手にしたブラジルのエネルギー事情は今後大きく改善し、ブラジル経済のさらなる推進力になるものと予想される。 『2011.1.12付三菱総研レポート』より
http://www.mri.co.jp/NEWS/column/thinking/2011/2025159_1799.html
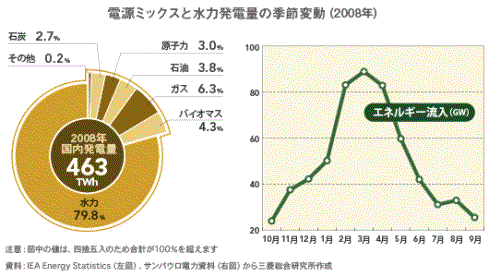 |
問3 9 ② 【良問】思考力を問う問題
韓国 造船は日本・韓国で世界の6割・中国をあわせて8割生産している。韓国は2008年で日本よりも生産量が10%の差をあけて1位である。
→唯一日本の2007年生産を上回っている点があるBが韓国。
また、サが2007年とわかる。
イギリス ドックランズの再開発に見られるように、イギリスは造船は停滞している。また、韓国の鉄鋼生産は6位(2009年)と上位でイギリスよりも生産量が少ないというのはおかしい→
キが2007年。
| 造船竣工量(千総㌧) |
|
粗鋼の生産(千㌧) |
| 国名 |
2000 |
% |
|
2007 |
% |
|
2009 |
% |
|
国名 |
2007 |
% |
|
2009 |
% |
| 世 界 |
31,696 |
100 |
|
57,320 |
100 |
|
77,073 |
100 |
|
世 界 |
1,344,265 |
100 |
|
1,219,715 |
100 |
| 韓国 |
12,218 |
38.5 |
|
20,593 |
35.9 |
|
28,849 |
37.4 |
|
中国 |
489,241 |
36.4 |
|
567,842 |
46.6 |
| 日本 |
12,001 |
37.9 |
|
17,525 |
30.6 |
|
18,972 |
24.6 |
|
日本 |
120,196 |
8.9 |
|
87,534 |
7.2 |
| 中国 |
1,484 |
4.7 |
|
10,553 |
18.4 |
|
21,969 |
28.5 |
|
アメリカ合衆国 |
98,181 |
7.3 |
|
58,142 |
4.8 |
| ドイツ |
975 |
3.1 |
|
1,362 |
2.4 |
|
781 |
1.0 |
|
ロシア |
72,220 |
5.4 |
|
59,940 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
インド |
53,080 |
3.9 |
|
56,608 |
4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韓国 |
51,367 |
3.8 |
|
48,598 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ドイツ |
48,550 |
3.6 |
|
32,671 |
2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ウクライナ |
42,830 |
3.2 |
|
29,757 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ブラジル |
33,784 |
2.5 |
|
26,507 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
『世界国勢図会』 |
問4 10 ② 【基本】消去法でも解ける 日本あり。様々な建設が進む中国が5割→セメント
① カナダ・フィンランド・スウェーデン →パルプ
③ ブラジル・インド→サトウキビ生産が多い→砂糖
④ フランス・イタリア →ワイン
問5 11 ④ 【易】 9 の統計にもあるように日本は生産2位。国際的な製鉄会社の再編はあるが、本文は間違い。
① 1985年のプラザ合意以降の円高対策と貿易摩擦解消のため、日本は自動車の現地生産を本格化させた。
② おなじく、円高による国際競争力の低下によって、労働集約型産業は低賃金のアジアへ工場を移転し、国内の空洞化が問題になった。
③ 1990年代後半にインターネットが普及し、ベンチャー企業が生まれた。ベンチャー企業は人材と情報を確保するため都市に立地した。
問6 12 ⑤ 【基本】
タ 繊維から先端技術産業→エレクトロニクスハイウェーの中心地ボストン
→M
チ 石油化学・NASA→メキシコ湾岸→K
ツ 周辺の鉱産資源(鉄鉱石・石炭)と鉄鋼・自動車→五大湖周辺→L
■ 8 は 4 をしっかり考えていれば、ヒントになっただろう。火力発電のエネルギー源をまともに考えると難しかった。 9 は多角的に資料を読み取る力が必要で、おもしろい問題である。全体を通して、標準的なレベルである。
第3問 (配点17点: 18 2点、他3点) 【生活文化と都市】
問1 13 ③ 【基本】通気性良く・高床式→D
① 厳しい寒さ・イズバ →C
② 樹木が少ない・日干しれんが →B
④ 強い日差し・白壁の石造り住居→A
問2 14 ① 【基本】
ア 人口最大・アジア・アフリカが中心→イスラーム
イ ヨーロッパ・ラテンアメリカが多い→カトリック
ウ 最も人口が少ない →プロテスタント
問3 15 ② 【基本】その国・都市の経済力を考える。ニューヨーク・ソウルは世界的大企業の本社が多いと考えるのが妥当。
① 本社数が多く、人口割合が少ない →ニューヨーク
② 本社数が多く、人口割合が多い →ソウル
③ 本社数が少なく、人口割合が少ない→上海
13億の人口で1割といえば1億。そんな都市はない。
④ 本社数が少なく、人口割合が多い →プラハ
問4 16 ④ 【基本】途上国はプッシュ型の人口移動を示すが、必ずしも都市へ行けば就職できるとは限らず、都市周辺部にスラム街が形成される。
① オーストラリアは移民が多く、黒人の割合は高くない。
② パリは伝統的な建物を保存したマレ地区がある。パリのクリアランス型はスラム街や市場を副都心(ラ・デファンス)、大規模商店街(レ・アール)、モンパルナス(オフィス街)にしている。
③ メキシコシティの郊外にはスラム街がある。途上国は都市周辺部にスラム街ができる傾向がある。
問5 17 ⑤ 【基本】
G 2次産業が最も高い →自動車工業の豊田
H 人口増加率がマイナス→地方都市の長崎
F 人口増加率が高い →大阪大都市圏の住宅都市の西宮
問6 18 ⑤ 【易】2004年本試第4問問7と同タイプの問題
東京へ通勤すると考えれば、都区部に近い方が割合は高い。
カ 南西に割合が高いところがある→K
キ 北東に割合が高いところがある→L
ク 高い割合がない →もっとも離れたク
■ 18 のような特徴的な問題で過去と同じタイプの問題がでている。過去問演習は大切というのがよくわかる。 13 のイズバやシドニーの都市構造のように教科書ではあまり扱わない内容があるが、問題を解くにはあまり影響がない。プラハや西宮といった地名がでてきたが、どこの都市かわからないと解答には困る。地名学習は大切といえる。地図帳を見ながら勉強して欲しい。
第4問 (配点18点:各3点) 【アフリカの地誌】
問1 19 ② 【良問】アフリカの標高は案外盲点になっているのでは。
大部分が楯状地になっている。海岸からすぐに標高が高くなっている。地図をよくみて、海岸から内陸へ順番に高くなっているように並び替えればできる。
ア もっとも海岸に近いところに分布している→500m~
ウ アについで、内陸にある。 →1100m~
イ アトラス山脈、アフリカ大地溝帯、エチオピア高原などの地域に分布
→1600m~
問2 20 ② 【基本】落花生・雑穀→B
① 小麦粉を粒状にし蒸したものはクスクス。オリーブ。→A
③ 米飯→D マダガスカル島の先住民は東南アジアのボルネオ島から移住してきた。マレー系のメリナ族が最大民族。
④ ヤムイモやバナナ→焼畑の作物→C
問3 21 ⑥ 【基本】
キ 北アフリカに分布なし→イスラム圏→豚
カ サハラ地域のみに分布 →駱駝
ク 東アフリカのサバナ地域など広範囲に分布。頭数も最大→牛
cf.マサイ族 ケニア南部~タンザニア北部に居住
問4 22 ③ 【基本】茶・切り花(薔薇)→ケニア 茶→ホワイトハイランド-南部の高原地域
① 魚介類 →モロッコのタコ
② 原油・天然ガス →アルジェリア
④ 銅・銅鉱 →ザンビア
問5 23 ⑥ 【やや難】
サ 交易の拠点だから港町中心。スワヒリ語だからケニア→R
象牙から象牙海岸を連想しPとしてしまいやすいので注意
シ 二つの気候帯は乾燥帯と熱帯。岩塩と森林産物 →Q
ス 植民地経営の行政拠点→各地に分散した分布 →P
問6 24 ⑤ 【基本】長い文章をよく読めばできる
タ 人種差別撤廃→南アフリカ共和国
チ 植民統治を受けていない。キリスト教はコプト教のこと→エチオピア
ツ イギリス植民地で周囲はフランス領→ガーナ
他のギニア湾諸国で英領はナイジェリア
■ 23 24 は知らないといってとまどったかもしれないが、冷静に文章を読んで判断しよう。アフリカの自然や農業をさまざまな資料をもとに問うた問題がそろっている。基本的なことを問うているが、資料を正確に読む力が試されており、正答率は低そうである。
第5問 (配点15点:各3点) 【現代の諸課題】
問1 25 ② 【基本】
A 1950年から急増→アフリカ
B 安定的に増加 →ヨーロッパ
C 2000年時点で約3億人→北米 アメリカ3億弱+カナダ3000万人
2009年時点でアメリカは3億1500万人
問2 26 ④ 【基本】
① 穀物自給率高い、カロリー最大、低死亡率→ドイツ
② 穀物自給率高い、高死亡率→インド 米・小麦世界生産2位
③ 穀物自給率低い、中死亡率→サウジアラビア 砂漠の灌漑耕地
④ 穀物自給率低い、低死亡率→韓国 日本と同じく飼料を輸入
問3 27 ⑤ 【基本】
P 1990年代の国家体制変革→ソ連崩壊 →ロシア連邦
Q 干ばつによる飢餓、文化・言語の対立 →スーダン
cf.ダルフール紛争「最大規模の人道危機」といわれる
R 軍事政権、民主化運動の政治的迫害(アウンサン・スーチー女史)
→ミャンマー
問4 28 ③ 【基本】ODA比率0.7%越え→オランダ 北欧ほど比率が高い
② アジア→日本
① 総額、サハラ以南のアフリカ →フランス 元植民地関連
④ 総額少ない、西アジアや北アフリカ→イタリア
問5 29 ② 【易】
カ 酸性雨の越境汚染→E
キ 森林伐採と希少生物の絶滅→G
ク 世界最大規模のダムはサンシャダム→F
■オーソドックスな問題がほとんど。問題数も少なく、余裕があったのではないか。
第6問 (配点16点: 34 35 各2点、他3点) 【佐賀市を中心とした地域調査】
問1 30 ② 【易】
① 蛇行のあとは水田のいびつな区画から判断できる。八町は自然堤防上にあり、旧河道に挟まれている
② 植生界からこの地形図は25000分の1。2kmというと8cmなければいけないが、あきらかにそれほどない。実際は5cm。
③ 本文・地勢図から干拓地とわかる。地図に0mの点があり、0m以下である。
④ 縦横無尽に水路がある。自然の川と違い直線的である。水田の中にあることから、農業用クリークである。
問2 31 ③ 【易】新旧地形図の読図
① 地図記号問題。水田が住宅に変わった。
② 本荘付近に新たな道路が建設されている。北部の国道から分かれ、平行にあることからバイパスは判断できる。
③ 寺院はいくつかあるが、ほとんど残っている。
④ 水路は明らかに屈曲していたが、直線的になっている。
問3 32 ② 【易】
① 業種構成は商業統計表などで調べられる。
② 空中写真から通勤のような動態的なものを調べるのは不可能。
③ 役所で立地傾向の聞き取りは可能。
④ 過去は文献史料をあたるのがよい。
問4 33 ④ 【基本】
F 広い敷地に大きな駐車場と店舗 →ロードサイド店→ウ
G 空き店舗と狭い店舗が道路沿いに並ぶ→商店街 →ア
H 高層の建物や金融機関が立地している→CBD →イ
問5 34 ③ 【基本】
J 広く分布 →水稲 日本は水田がいろいろなところにある
L 丘陵地に分布→ミカン
K 残り →大麦 米の裏作として栽培
問6 35 ⑤ 【基本】
カ サービス業中心。英語表記 →フィリピン
キ 著しい経済成長、留学生、研修生。通貨単位が元→中国
ク 数世代にわたり居住、国籍取得。ハングル →韓国・朝鮮
R 本文にあるように入国審査が厳格化→近年減少 →フィリピン
Q 以前から人口が多く、やや減少 →韓国・朝鮮
P 近年増加が続いている。留学生・研修生の増加 →中国
■地域調査らしい問題だが、やや易しい問題が多い。 33 の図は地域調査らしい図といえる。 34 は地勢図の地形を見て慎重に解く。 35 はそれぞれを判断したうえでの組合せなので難しそうだが、実際はすぐに判別できる。
●出題形式
|
| |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
| 単 答 式 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
| 図 中 選 択 |
0 |
1 |
3 |
0 |
3 |
| 文 選 |
14 |
14 |
13 |
11 |
8 |
| 文章中の正誤判別 |
0 |
0 |
2 |
5 |
0 |
| 組 合 せ |
4 |
6 |
5 |
5 |
8 |
| 統 計・組合せ |
14 |
5 |
7 |
7 |
10 |
| 単答式 |
3 |
6 |
1 |
7 |
5 |
| 雨温図・組合せ |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 単答式 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| ハイサー・組合せ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 単答式 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 気候表・組合せ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 単答式 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 写 真の枚数 |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
| 地形図の枚数 |
4 |
3 |
2 |
3 |
7 |
| 読図関連 |
4 |
2 |
3 |
3 |
2 |
| 図表読み取り |
0 |
2 |
4 |
5 |
0 |
| 計 算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
●大問6題で変わらず。大問ごとのテーマは昨年と同様。総問題数は一昨年は37問に増加、昨年は36問に戻り、今年は35問に減少。
●地理Aとの共通問題は第6問の地域調査と地球的課題の2問であった。
●地域調査は第2問へ移動。
●図表の単純な読み取り問題がなくなった。地理の知識がいらない問題だけに、よかったのではないか。
●文選が減少し、組合せ問題が増加している。
●地形図がふんだんに使われた。小さな地形図でも地形の様子を読み取る力は必要である。
●昨年は疑問符がつくような問題もあったが、今年はそのような問題はなかった。地理の学習をしっかりしておけば、ちゃんと点数のとれる問題であった。そのため、昨年より易しいイメージであるが、図表読み取りがなくなったため、難易度は昨年並みではないか。
地理A 第5問は地理B第6問と共通
第1問 (配点21点: 3 6 8 各2点、他2点) 【地理の基礎的事項】
問1 1 ④ 【基本】図からA地点の経度は45度。東京都の時差は12時間である。
A地点は東京より西側にあるので、
1/1 13:00+12=1/1 25:00→1/2 1:00
問2 2 ③ 【基本】
E ロサンゼルス CsとBSの境界。現在のデータではBS
F ダカール BSとBWの境界。現在のデータではBW
G シャンハイ Cfa
H パース Cs
|
都 市 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
| 46 |
Los Angeles(38m) |
14.1 |
14.8 |
15.2 |
16.8 |
18.1 |
20.2 |
22.3 |
23.0 |
22.3 |
20.1 |
16.8 |
14.2 |
18.2℃ |
|
(33゚56'N,118゚24'W) |
74.7 |
72.4 |
61.6 |
20.2 |
1.4 |
3.0 |
0.9 |
2.7 |
8.7 |
8.0 |
31.5 |
41.9 |
326.9mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 |
Dakar(27m) |
20.5 |
20.2 |
20.6 |
21.1 |
22.4 |
25.4 |
26.9 |
27.3 |
27.5 |
27.4 |
25.4 |
22.6 |
23.9℃ |
|
(14゚44'N,17゚30'W) |
0.6 |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
8.8 |
54.1 |
141.8 |
121.9 |
21.4 |
1.0 |
1.1 |
351.4mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92 |
上海(8m) |
4.3 |
5.3 |
8.8 |
14.5 |
19.6 |
23.7 |
27.9 |
27.7 |
23.7 |
18.7 |
12.8 |
6.7 |
16.1℃ |
|
(31゚24'N,121゚28'E) |
81.1 |
37.1 |
98.9 |
60.8 |
88.3 |
171.8 |
140.1 |
255.1 |
83.1 |
57.0 |
46.4 |
35.3 |
1155.1mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 199 |
Perth(20m) |
24.5 |
24.9 |
23.0 |
19.6 |
16.2 |
14.0 |
13.1 |
13.4 |
14.6 |
16.4 |
19.3 |
22.1 |
18.4℃ |
|
(31゚56'S,115゚58'E) |
6.6 |
18.8 |
16.3 |
36.3 |
93.5 |
147.8 |
149.3 |
117.7 |
78.8 |
45.3 |
26.7 |
8.1 |
745.4mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(『理科年表
平成20年版』) |
問3 3 ① 【基本】
ア アフリカ楯状地→安定陸塊
イ ザグロス山脈 →新期造山帯
ウ 古期造山帯
エ 環太平洋造山帯→新期造山帯
問4 4 ③ 【基本】アメリカ合衆国との国境 リオグランデ川
① チリとの国境 アンデス山脈
② ノルウェーとの国境 スカンディナビア山脈
④ エジプトとの国境 東経25度
問5 5 ① 【基本】ずいぶんおおざっぱな印の付け方
インドネシアはイスラームが8割、マレーシアは6割。
問6 6 ④ 【基本】セーヌ川。放射環状型道路
① 皇居
② ハドソン川・イースト川に挟まれたマンハッタン。直交路型街路。
③ 紫禁城。格子状の道路
問7 7 ① 【基本】基本的な土地利用を問う問題
★ 段丘の上に分布。乏水地に多い畑。
▲ 川沿いの沖積平野に分布。水の得やすいところに多い水田。
● 崖や海岸線に沿ってある防風林・防砂林→針葉樹
問8 8 ④ 【良問】おもしろい。イギリスは壺型になるので、うまく壺になるように考える。
ツ 壺がたは一番下が細くなる形。これが一番下。
チ 上に行けば徐々に細くなる。これが一番上。
■配点が昨年16点から今年21点と増加。従来同様、基礎的事項は地理Aのみ。毎年、投影法に関して出題されていたが、今年は時差。単純に気候区や地帯構造を問う問題がみられる。問8は人口ミラミッドを分解したおもしろい問題だった。
第2問 (配点21点:各3点) 【国教を超えた様々な結びつき】
問1 9 ④ 【良問】同様の考え方の問題は多いが、世界地図レベルで出すのはおもしろい。図の作成は大変だったろう。
① カナダ・メキシコのNAFTA加盟国あり →アメリカ
② オーストラリア・東南アジア →日本
③ スペイン・ギニア湾岸やマダガスカルの旧仏領→フランス
④ 残り。ヨーロッパ・ロシア→ドイツ
問2 10 ② 【基本】
A 1965年天然ゴム、2005年石油・天然ガス→インドネシア
B 1965年錫・木材、2005年合板→マレーシア
C 1965年米・2005年魚介類→タイ
問3 11 ③ 【良問】
① 比較的広い地域に10位都市が集まる→アジア→東京
③ 比較的狭い地域に10位都市が集まる→欧州 →ロンドン
② アジアとヨーロッパの間→西アジア→ドバイ
④ 欧州と大西洋を隔てたところにある→ニューヨーク
アメリカは国内に限れば多くの航空路線がある。問題は国際路線なので注意が必要。
<単純に経度だけで考える>←第1問の地図を活用
ロンドンを起点に東京は東経140度、ドバイは東経55度、ニューヨークは西経75度。
北極点から各都市に直線を引けば、経線になる。①~④までの都市をそれぞれロンドンとして、各都市の経度が合致するかを検討する。
① 仮にロンドンとすると、西経に2都市あることになり、不適
② 仮にロンドンとすると、西経に2都市あることになり、不適
③ 合致する
④ 仮にロンドンとすると、ニューヨーク90度以上の地点になり、不適
問4 12 ③ 【基本】近隣諸国との距離を考える
P 福岡で断トツ1位。各空港で上位→韓国
R 新潟のみ→ロシア
Q 沖縄のみ→アメリカ
問5 13 ④ 【基本】図はよい。問題は?と思う。
① 下線部のみを考えれば、間違いはない。図は関係ないように思える。下線部を問う意図がわからなかった。
② 一般的にそうといえる。ただ、図からは宗主国との関係を読み取ることは不可能。
③ ★のあるところは中央アジアやカナリヤ諸島、オセアニアにありとくに目立った産業はない。
④ 先端技術分野で途上国から先進国へいくのはインド。
問6 14 ② 【やや難】
④ 北アメリカが最大→先端技術の発達しているアメリカ→研究者
③ 総人数が最も少ない→報道関係者
② 総人数も少なく、その他地域が多い→世界各地にいる政府関係者
① 総人数が最も多く、アジアに多い→民間企業
問7 15 ④ 【易】鉄道と航空機に貿易が依存が誤り。貿易の主力は船舶。
① ヨーロッパは狭い範囲に国が集まっているため、各国を結ぶ陸上交通網は国を超えてつながっている。
② 海底パイプラインが敷設されている。
③ バンコクの渋滞は有名。公共交通機関のインフラ整備が欠かせない。
■図や問題に力作が多い。そのため、難易度は上がっている。地理Aにしてはかなりのレベル。地理Bでの出題でも良かったのではないか。
第3問 (配点21点:各3点) 【東アジアとその周辺地域の地誌】
問1 16 ③ 【基本】長江の記述。黄河は長さ国内2位。小麦などの畑作地帯。
① Aはチベット高原。家畜はヤク。
② Bはバイカル湖。Dw地域でタイガが広がる。
④ 台湾は昔からパイナップルやバナナが有名。
問2 17 ② 【基本】消去法で解く。内陸で降水量が少ない。BS 西安
① Cfa 福岡
③ Dw ウラジオストク
④ Cw 香港
|
都 市 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
| 42 |
Vladivostok(183m) |
-12.6 |
-9.2 |
-2.0 |
4.8 |
9.7 |
13.1 |
17.7 |
19.6 |
15.7 |
8.6 |
-1.0 |
-9.1 |
4.6℃ |
|
(43゚07'N,131゚56'E) |
0.6 |
0.9 |
2.2 |
6.8 |
28.3 |
70.1 |
113.2 |
113.8 |
60.2 |
10.5 |
1.4 |
1.1 |
409.1mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
西安(298m) |
0.0 |
3.0 |
8.2 |
14.9 |
19.9 |
24.9 |
26.7 |
25.4 |
20.0 |
14.1 |
7.0 |
1.4 |
13.8℃ |
|
(34゚18'N,108゚56'E) |
6.9 |
10.3 |
28.7 |
42.8 |
60.0 |
54.2 |
98.6 |
70.8 |
91.7 |
60.0 |
24.8 |
7.0 |
281.8mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J66 |
福岡(2.5m) |
6.4 |
6.9 |
9.9 |
14.8 |
19.1 |
22.6 |
26.9 |
27.6 |
23.9 |
18.7 |
13.4 |
8.7 |
6.6℃ |
|
(33゚34.9'N,130゚22.5'E) |
72.1 |
71.2 |
108.7 |
125.2 |
138.9 |
272.1 |
266.4 |
187.6 |
175.0 |
80.9 |
80.5 |
53.8 |
1632.3mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 |
香港(65m) |
16.3 |
16.2 |
18.8 |
22.6 |
25.6 |
27.8 |
28.3 |
28.1 |
27.2 |
25.1 |
21.7 |
18.0 |
23.0℃ |
|
(22゚19'N,114゚10'E) |
26.8 |
50.3 |
42.6 |
184.9 |
222.5 |
428.6 |
407.6 |
526.3 |
280.3 |
124.1 |
31.4 |
35.0 |
2360.4mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(『理科年表
平成20年版』) |
問3 18 ④ 【易】
ア コウリャン・大豆→G
イ 二期作→H
ウ オアシス→F
問4 19 ① 【基本】間違えやすいか。人口増加率が最も高い→モンゴル
② 女性の割合が低い。→中国 一人っ子政策で人口増加率は高くない。
一人っ子なので、子どもは男子を望む。
④ 人口増加率が最も低い・幼年人口割合が低い→人口減少社会・少子化
③ 残り。韓国
問5 20 ② 【基本】台湾は半導体・ICなどの産業が発達している。水産物はまぐろなどがあるが、貿易上位にない。
① ハンガンの奇跡は工業、セマウル運動は農業。
③ 近年は内陸の開発に力をいれ、経済格差の解消にむけて努力している。
④ 日本も参加したサハリン開発。パイプラインとタンカーで石油を輸入している。
問6 21 ③ 【易しい】
サ 床暖房→韓国のオンドル→K
シ フェルトのテント→モンゴル民族のゲル→J
ス 白川郷などの合掌造り→日本→L
問7 22 ④ 【やや難】
タ 観光客の受入数が最大、受入数の伸び率2.5倍→中国
チ 観光客の受入数の伸び率が低率→香港
ツ 日本とほぼ同じ→韓国
■易しい問題とやや難しい問題の差が大きい。地理Aにとっては 19 や 20 もやや難しいか。
第4問 (配点21点:各3点) 【地球的課題と国際協力】
問1 23 ② 【易】地理B 29 と共通問題
カ 酸性雨の越境汚染→E
キ 森林伐採と希少生物の絶滅→G
ク 世界最大規模のダムはサンシャダム→F
問2 24 ③ 【易】スマトラ島沖地震のこと。
問3 25 ③ 【基本】
④ 原子力が多い→フランス
① 石炭が多い→中国
③ 水力が多い→カナダ
② 残り→日本
問4 26 ④ 【基本】単純な図の読み取りを工夫した問題。図を見なくても解けてしまうのが残念。 19 (中国)とかぶっている感じを受ける。
◇ 80年代まで伸びているが、それ以降は横ばい→スウェーデン→②
● ずっと伸びており、最新で20%近くの超高齢社会→日本→①
■ 90年くらいまで穏やかに上昇、その後、やや上昇傾向→中国→③ ←人口増加期は老齢人口は停滞するが、一人っ子政策が浸透すると若年層がへり、老齢人口が穏やかに上昇する
▲ ずっと停滞→ナイジェリア→④ 外国人労働者の移民よりも多産傾向が強い。
問5 27 ② 【やや難】地理Aでは瀋陽やジャカルタといった地名を知らないかも
① 近隣にフーシュン(撫順)炭田やアンシャン(鞍山)鉄山がある。
② 途上国は首都に経済機能が集まり、地価高騰の原因になっている。地方へ機能が移転していない。
③ 梅雨末期の集中豪雨や台風などで起こる。アスファルトに覆われ、地面に浸透せず、都市の排水機能を超えた時に起こる。
④ ドックランズのこと。
問6 28 ⑤ 【基本】地理B 27 と共通問題
P 1990年代の国家体制変革→ソ連崩壊 →ロシア連邦
Q 干ばつによる飢餓、文化・言語の対立→スーダン
cf.ダルフール紛争「最大規模の人道危機」といわれる
R 軍事政権、民主化運動の政治的迫害(アウンサン・スーチー女史)
→ミャンマー
問7 29 ④ 【やや難】
S 他と比べベトナム・モンゴルが多い→アジア中心→日本
T コートジボワール・ベトナムが多い→フランス←旧植民地
U ボリビアが多い→南米→アメリカ合衆国
■地域調査以外に地理Bとの共通問題が2題あった。地名学習が必要な問題もある。全体的には易しい問題もあり、標準的。
第5問 (配点16点: 34 35 各2点、他3点) 【佐賀市を中心とした地域調査】 (地理B第6問と共通問題)
問1 30 ② 【易】
① 蛇行のあとは水田のいびつな区画から判断できる。八町は自然堤防上にあり、旧河道に挟まれている
② 植生界からこの地形図は25000分の1。2kmというと8cmなければいけないが、あきらかにそれほどない。実際は5cm。
③ 本文・地勢図から干拓地とわかる。地図に0mの点があり、0m以下である。
④ 縦横無尽に水路がある。自然の川と違い直線的である。水田の中にあることから、農業用クリークである。
問2 31 ③ 【易】新旧地形図の読図
① 地図記号問題。水田が住宅に変わった。
② 本荘付近に新たな道路が建設されている。北部の国道から分かれ、平行にあることからバイパスは判断できる。
③ 寺院はいくつかあるが、ほとんど残っている。
④ 水路は明らかに屈曲していたが、直線的になっている。
問3 32 ② 【易】
① 業種構成は商業統計表などで調べられる。
② 空中写真から通勤のような動態的なものを調べるのは不可能。
③ 役所で立地傾向の聞き取りは可能。
④ 過去は文献史料をあたるのがよい。
問4 33 ④ 【基本】
F 広い敷地に大きな駐車場と店舗 →ロードサイド店→ウ
G 空き店舗と狭い店舗が道路沿いに並ぶ→商店街 →ア
H 高層の建物や金融機関が立地している→CBD →イ
問5 34 ③ 【基本】
J 広く分布 →水稲 日本は水田がいろいろなところにある
L 丘陵地に分布→ミカン
K 残り →大麦 米の裏作として栽培
問6 35 ⑤ 【基本】
カ サービス業中心。英語表記 →フィリピン
キ 著しい経済成長、留学生、研修生。通貨単位が元→中国
ク 数世代にわたり居住、国籍取得。ハングル →韓国・朝鮮
R 本文にあるように入国審査が厳格化→近年減少 →フィリピン
Q 以前から人口が多く、やや減少 →韓国・朝鮮
P 近年増加が続いている。留学生・研修生の増加 →中国
■地域調査らしい問題だが、やや易しい問題が多い。 33 の図は地域調査らしい図といえる。 34 は地勢図の地形を見て慎重に解く。 35 はそれぞれを判断したうえでの組合せなので難しそうだが、実際はすぐに判別できる。例年、地域調査では最後の第7問が地理Aのみの問題だったが、今年はなかった。
●出題形式
|
|
| |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
| 単 答 式 |
4 |
4 |
6 |
3 |
3 |
| 図 中 選 択 |
1 |
4 |
1 |
2 |
3 |
| 文 選 |
8 |
11 |
12 |
8 |
9 |
| 文章中の正誤判別 |
0 |
0 |
2 |
5 |
1 |
| 組 合 せ |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
| 統 計・組合せ |
9 |
4 |
6 |
5 |
7 |
| 単答式 |
6 |
2 |
2 |
5 |
5 |
| 雨温図・組合せ |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 単答式 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
| ハイサー・組合せ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 単答式 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 気候表・組合せ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 単答式 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 写 真 |
2 |
3 |
3 |
10 |
3 |
| 地形図の枚数 |
3 |
4 |
2 |
3 |
7 |
| 読図関連 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
| 図表読み取り |
1 |
3 |
3 |
4 |
2 |
| 計 算 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
●出題のテーマは昨年とほぼ変わっていない。問題数は昨年より1問減少している。Bとの共通問題が昨年より2問増加している。単純な図表の読み取りがへり、統計問題が増加した。また、判別も難しいものも多く、昨年より難易度は上がっている。全体の難易度が上がっているためか、第1問の配点が昨年より増えている。そのため平均は昨年並みに落ち着いたのか?第2問は地理Bでもいいような問題で、良問も多く、地理B選択者も地理Aの問題に目を通すのがよい。